インフルエンザ予防接種の時期になると、0歳児のお子さんを育てるお母さんから、予防接種のタイミングに関して質問されることがあります。特に初めてのお子さんだと気になりますよね。今回はインフルエンザ予防接種の時期に関してお伝えしたいと思います。

「小児科オンラインジャーナル」は、お子さんの健康に関する様々な情報を発信しています。病気の症状や原因、対処法はもちろん、予防接種や健診、子どもの成長に関する豆知識まで、小児科医が分かりやすく解説しています。

インフルエンザ予防接種の時期になると、0歳児のお子さんを育てるお母さんから、予防接種のタイミングに関して質問されることがあります。特に初めてのお子さんだと気になりますよね。今回はインフルエンザ予防接種の時期に関してお伝えしたいと思います。

麻疹(ましん、通称「はしか」)の怖いところは「とても強い感染力」、そして予防するには「本人そして周りのワクチン接種」が大切です。麻疹の症状またワクチンを打つ大切さを確認していきましょう。

時折ニュースでも取り上げられる「麻疹」(ましん、通称「はしか」)という感染症に対して漠然と不安を持っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
実はこの感染症、2008年の時点では国内で年間1万人強の感染者がいました。その後予防接種の2回接種が徹底され、感染者数自体は激減しました。
しかし、どうしても国境を超えた人の往来がある現代において、国外から持ち込まれることは防ぎきれません。万が一持ち込まれた場合に、その広がりを最小限に食い止めるためにできることは、子どもから大人までしっかり予防接種をしておくことです。

「黄色い鼻水が出て、なかなか治りません」「もう数ヶ月も鼻水が出続けています」といった相談は、保護者の方からとてもよく寄せられます。今回は長引く鼻水と副鼻腔炎の関係についてお伝えしようと思います。



「ヒトメタニューモウイルス」このあまり耳慣れないウイルスについて知っていますか?このウイルスは、ずっと昔から存在したと考えられていますが、発見されたのは2001年とかなり最近です。その後、外来で簡単に検査できるキットが開発されたため、ヒトメタニューモウイルス感染症と診断される機会が増えています。余計な心配をしないで済むように、この得体の知れないヒトメタニューモウイルスとその感染症についてご紹介します。
続きを読む
「風邪を早く治したいので、抗生剤をいただけませんか?」「念のため抗生剤をいただけませんか?」そんなご要望を外来で伺うことがあります。お気持ちはわかります。お子さんが早く良くなることは小児科医含め誰もが望んでいることです。しかし、風邪に抗菌薬を使うことでそれが達成されるわけではありません。(抗生剤という呼び名のほうが耳慣れているかもしれませんが、正しくは、抗菌薬と呼びます。)

「インフルエンザのワクチンって、意味あるのですか?」という質問をご家族から受けることがあります。「年によって変動しますが、だいたいインフルエンザワクチンは有効率60%ぐらいで、効果がありますよ」とお答えすると、「ほらやっぱり、そんなに低いなら打ちたくないです」という感想を言われることがあります。
しかし、それは本当に低いのでしょうか?
そんなことはありません。
本記事ではインフルエンザワクチンの有効率に関してご紹介しようと思います。

お子さんが、犬が吠えるような咳をしたことはありませんか?オットセイの鳴き声のような咳と表現されることもあります。この特徴的な咳が出る状態は「クループ」と呼ばれ、注意が必要です。時間帯としては、夜間や早朝によく起きます。

インフルエンザの流行期になると、インフルエンザについて調べたり、説明を受ける機会が増えますよね。その際に、説明に用いられる用語がややこしくて混乱してしまった経験はありませんか?医療関係者は正確なことを伝えるために、一見するとややこしい用語を使い分けているので、その一部を整理してご紹介しますね。

おたふくかぜによって、約1000人に1人の割合で難聴になることがあります。おたふくかぜは耳の下のほほが腫れる病気で、ほとんどの場合は、何事もなく自然に治ります。しかし、その一部には難聴のような、大きな合併症も起きることをご存知ですか?

秋も深まり、しばらくするとインフルエンザが流行する季節となります。
インフルエンザになると、38℃を超える熱や頭痛、関節や筋肉の痛み、全身のだるさなどが急激に出現します。5歳未満のお子さんがインフルエンザウイルスに感染すると、急性脳症や肺炎などの合併症が大人に比べて多いことが知られています。
今回はお子さんのインフルエンザ予防に関して、どんなことができるかお伝えします。

マイコプラズマと診断されたけれど薬を処方されなかった、抗菌薬を処方されたけれどなかなか症状がよくならない、といったお話を聞くことがあります。それらはどういうことなのでしょうか。お薬は、効果と副作用のバランスが重要ですが、マイコプラズマにおいても同様です。今回はそれらを踏まえて、マイコプラズマにおける抗菌薬の治療をご紹介します。

マイコプラズマという言葉を耳にしたことがあるでしょうか?
マイコプラズマは、学童期の肺炎の原因となる身近な病原体の1つです。実際に学校や職場でも流行することは珍しくありません。しかし、インフルエンザ程はあまり知られておらず、あまり聞き慣れないマイコプラズマという診断をされて不安になる方もいるのではないでしょうか。
今回、そのマイコプラズマとはなんなのかということと、風邪との違いをご紹介します。

ニュースで名前が流れることもあり、なんとなく聞き馴染みの出てきたRSウイルス。RSウイルス自体はありふれていて、1歳までに50%、2歳までにほぼ100%のお子さんが感染します。このウイルスに関して、年齢による症状の違い、そして日常での注意点についてお伝えします。

暑い日が続いていますね。この時期に流行るのは、手足口病、ヘルパンギーナといった、いわゆる「夏風邪」たちです。
いずれも特効薬がなく、熱さましを使いながら様子を見るしかない病気です。特別に病原性が高いというわけではないので、もしかかってしまっても、悲観的になりすぎる必要はありません。ただ、普通の風邪よりも、食事を痛がって、固形物を食べたがらない様子はありませんか?

夏の暑い時期になり、涼しい格好で遊んだり、プールに入ったりと肌を露出する機会が多くなります。そんな季節だからこそ、
「子どもに水いぼができた!どうすればいいの?」
「お友達にはうつるの?」
「予防するにはどうすればいいの?」
といったことが気になりますよね。まずは、次の3つのことを確認しておきましょう。

高温多湿の季節になってきました。この時期に増えるのが、お子さんの「とびひ」です。とびひを防ぐために生活で気をつけるべきことをお伝えします。まず、とびひの原因、からご説明します。
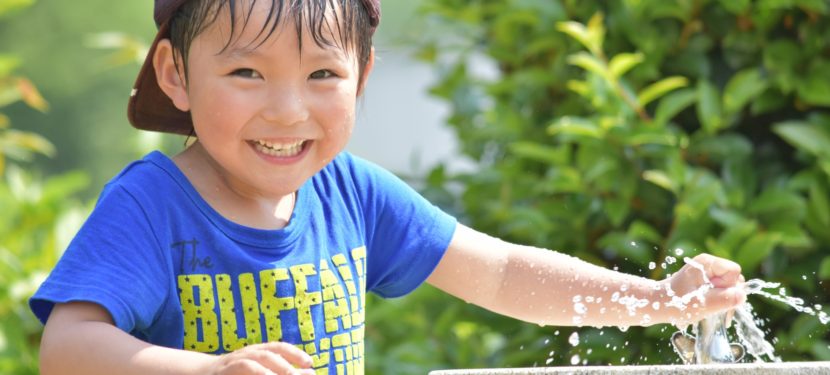
そろそろ本格的な夏の時期がやってきますね。保育園や幼稚園、小学校ではプールが始まり、夏休みももうすぐです。お子さんたちはウキウキ、ただこの時期にも子ども特有の感染症があるってご存知ですか?