「黄色い鼻水が出て、なかなか治りません」「もう数ヶ月も鼻水が出続けています」といった相談は、保護者の方からとてもよく寄せられます。今回は長引く鼻水と副鼻腔炎の関係についてお伝えしようと思います。

「小児科オンラインジャーナル」は、お子さんの健康に関する様々な情報を発信しています。病気の症状や原因、対処法はもちろん、予防接種や健診、子どもの成長に関する豆知識まで、小児科医が分かりやすく解説しています。

「黄色い鼻水が出て、なかなか治りません」「もう数ヶ月も鼻水が出続けています」といった相談は、保護者の方からとてもよく寄せられます。今回は長引く鼻水と副鼻腔炎の関係についてお伝えしようと思います。



「ヒトメタニューモウイルス」このあまり耳慣れないウイルスについて知っていますか?このウイルスは、ずっと昔から存在したと考えられていますが、発見されたのは2001年とかなり最近です。その後、外来で簡単に検査できるキットが開発されたため、ヒトメタニューモウイルス感染症と診断される機会が増えています。余計な心配をしないで済むように、この得体の知れないヒトメタニューモウイルスとその感染症についてご紹介します。
続きを読む

ようやく寒い冬が終わり、春の訪れを少しずつ感じるこの頃です。みんなが待ち望む春ですが、そんな季節にも悩みの種はつきません。そうです、花粉症です。正確には季節性アレルギー性鼻炎といいます。今回は花粉症を含む、子どものアレルギー性鼻炎にスポットをあててみたいと思います。

「風邪を早く治したいので、抗生剤をいただけませんか?」「念のため抗生剤をいただけませんか?」そんなご要望を外来で伺うことがあります。お気持ちはわかります。お子さんが早く良くなることは小児科医含め誰もが望んでいることです。しかし、風邪に抗菌薬を使うことでそれが達成されるわけではありません。(抗生剤という呼び名のほうが耳慣れているかもしれませんが、正しくは、抗菌薬と呼びます。)

嫌いな音で耳をふさぐ、偏食が強い、落ち着いて座っていられない。お子さんのこんな行動が気になったことはありませんか?
もしかすると感覚の受け取り方の違いに起因するものかもしれません。症状や対処法について考えてみたいと思います。

「インフルエンザのワクチンって、意味あるのですか?」という質問をご家族から受けることがあります。「年によって変動しますが、だいたいインフルエンザワクチンは有効率60%ぐらいで、効果がありますよ」とお答えすると、「ほらやっぱり、そんなに低いなら打ちたくないです」という感想を言われることがあります。
しかし、それは本当に低いのでしょうか?
そんなことはありません。
本記事ではインフルエンザワクチンの有効率に関してご紹介しようと思います。



赤ちゃんが世の中にすこしづつ慣れてきて、身の回りの物に興味を持ち始めると、どんなものでも口にして、場合によっては飲み込んでしまうこと(誤飲)があります。およそ4歳くらいまでの子どもはママたちがあっと驚くような物まで飲み込んでしまいます。
今回はその中でも特に気をつけなければならないものを紹介します。
また飲み込んだかわからない場合にどのような症状が見られたら、病院を受診すべきかもお伝えします。

お子さんが、犬が吠えるような咳をしたことはありませんか?オットセイの鳴き声のような咳と表現されることもあります。この特徴的な咳が出る状態は「クループ」と呼ばれ、注意が必要です。時間帯としては、夜間や早朝によく起きます。

清潔にしていてもすぐにめやにが出る、めやにが多くて目が開かない、いつも片方の目だけめやにが出るのはなぜ?悩む保護者の方は多いと思います。今回は赤ちゃんのめやにの原因と対処法をまとめました。
続きを読む
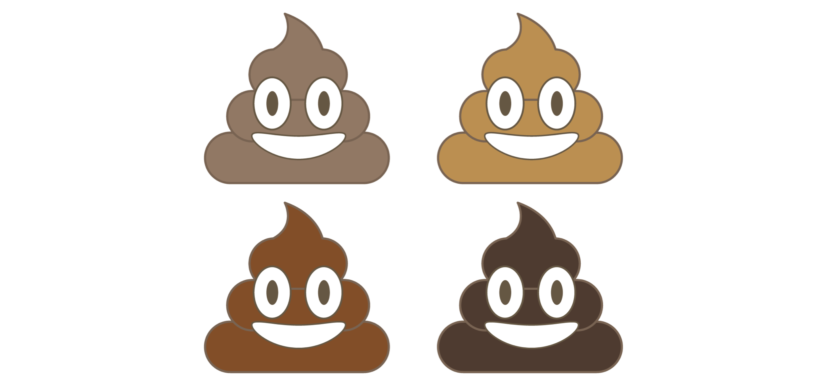
「赤ちゃんのうんちって何色が普通なの?」「生まれた時は黒かったのに、今は黄色っぽいけれど…」「確か白いうんちは危険なサインって言われたっけ?」「最近は緑のうんちもしてるよなー、大丈夫かなー?」
生まれてまもない赤ちゃんは言葉では体の不調を訴えられません。そのため赤ちゃんの哺乳量や機嫌、そして、うんちの色は赤ちゃんの体調をチェックする良い指標となります。
今回はそんな疑問をもつママたちへ、赤ちゃんのうんちの色からわかることをお答えします。

イヤイヤ期、とうとう来たか…
聞いてはいたけれど、こっちがイヤ!になってしまいそう。
今回はそんなイヤイヤ期をちょっと前向きにとらえるコツについて、子どもの発達の視点からお伝えします。

インフルエンザの流行期になると、インフルエンザについて調べたり、説明を受ける機会が増えますよね。その際に、説明に用いられる用語がややこしくて混乱してしまった経験はありませんか?医療関係者は正確なことを伝えるために、一見するとややこしい用語を使い分けているので、その一部を整理してご紹介しますね。

おたふくかぜによって、約1000人に1人の割合で難聴になることがあります。おたふくかぜは耳の下のほほが腫れる病気で、ほとんどの場合は、何事もなく自然に治ります。しかし、その一部には難聴のような、大きな合併症も起きることをご存知ですか?

秋も深まり、しばらくするとインフルエンザが流行する季節となります。
インフルエンザになると、38℃を超える熱や頭痛、関節や筋肉の痛み、全身のだるさなどが急激に出現します。5歳未満のお子さんがインフルエンザウイルスに感染すると、急性脳症や肺炎などの合併症が大人に比べて多いことが知られています。
今回はお子さんのインフルエンザ予防に関して、どんなことができるかお伝えします。

マイコプラズマと診断されたけれど薬を処方されなかった、抗菌薬を処方されたけれどなかなか症状がよくならない、といったお話を聞くことがあります。それらはどういうことなのでしょうか。お薬は、効果と副作用のバランスが重要ですが、マイコプラズマにおいても同様です。今回はそれらを踏まえて、マイコプラズマにおける抗菌薬の治療をご紹介します。