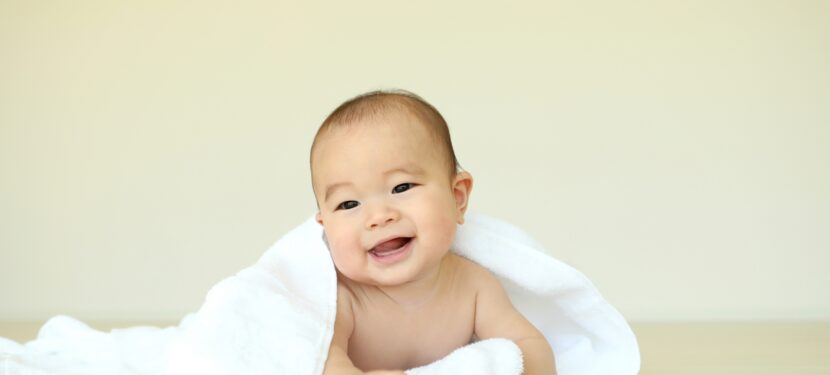
成長
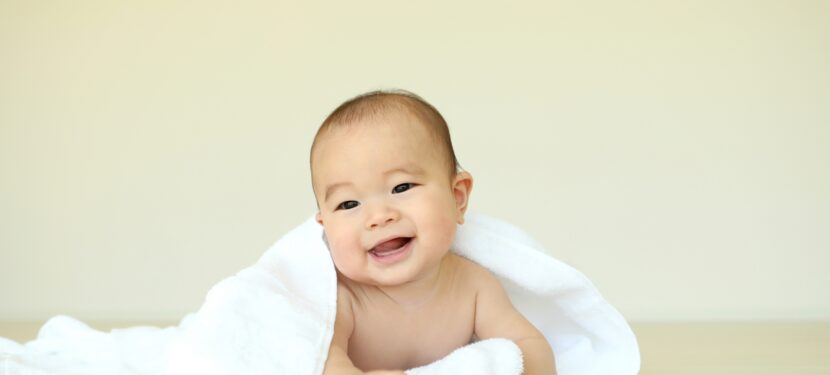

実は、日本の小児科学会も世界保健機関(WHO)も米国小児科学会(AAP)も「フォローアップミルク」は不要という見解です。結論としては、フォローアップミルクを使う必要はないのですが、この記事ではそのフォローアップミルクがどんなものかご説明します。

小児科の外来で体格に関するご相談を受ける際、低身長や過体重に比べて、「やせているかも?」というご相談はやや少ない印象です。しかし、不健康なやせは子どもの生活の質に大きく関わります。

生後6ヶ月を過ぎてくると、健診や母子手帳の説明に「おすわり」が登場してきますね。
まだグラグラするけど、大丈夫?おすわりしようとしないけど、平気なの?などの、よくあるお悩みについて解説します。

突然びくっとしたり、手や足をわなわなふるわせたり、小さいお子さんの思わぬしぐさに、どきっとすることがありますよね。「これってけいれんなの?」「受診するべき?」そんな疑問にお答えします。
続きを読む


思いがけず早産になってしまったり、出産時に赤ちゃんの具合が悪くてNICUに入院になったりすると、とても不安ですよね。
赤ちゃんはどのような状態になったら退院できるのでしょうか?


「体重、ちゃんと増えているかな?」「おっぱいやミルク、足りているのかな?」毎日の子育ては心配が尽きないですよね。
この記事では、生後すぐ〜6ヶ月くらいのお子さんについて、体重増加の考え方をご紹介します。
※ 早産でお産まれのお子さんについては、「早産児の体重増加の考え方」もあわせてご覧ください。

生まれた赤ちゃんが早産児、低出生体重児の場合、NICU退院後に様々な不安や心配をお持ちかと思います。早産で生まれても、目の前のお子さんは目覚ましいスピードで発達、発育しているのですが、ご両親が想像していたお産や子育てと違ってしまったことで、心配な気持ちが上回ってしまうことも多いでしょう。
今回は体重増加・発育の考え方について、低出生体重児保健指導マニュアルに沿ってお話ししていきたいと思います。

思春期が始まる時期には個人差があります。ただし、一定の時期より早かったり遅かったりする場合には、治療が必要な病気が隠れていることがあります。今回は思春期が遅めの場合の注意点についてお話しします。
早めの場合は「この年齢で思春期?ー早く思春期がきたときに考えるべきこと」をご参照ください。

中長期的に日常生活で自粛が必要となってしまったため、お子さんも普段の運動ができなくなってしまったかと思います。そのせいで生活のリズムもいつもより不規則になってはいないでしょうか?
今回は特に学童期のお子さん(6歳〜12歳)の成長にとって大事な「運動」に関してお伝えします。

お子さんの身長が周囲のお子さんよりも低いかもしれないと思ったとき、このまま様子をみていていいのか心配になることがありますよね。身長が低いことは必ずしも病気ではありませんが、ここでは身長が低いことの原因と、どんなときに病院へ受診されたほうがよいかについて解説します。










